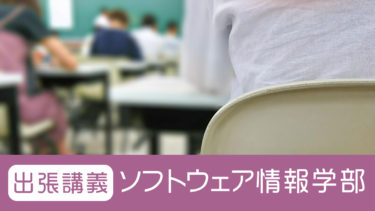忍者の秘密
津軽と南部地方に実在した忍者を紹介し、その活動実態を明かします。
中高生向け
忍者の秘密
津軽と南部地方に実在した忍者を紹介し、その活動実態を明かします。
陸奥湾にやってくるイルカの謎
毎年春になると陸奥湾にイルカの大群が現れます。なぜ陸奥湾にイルカが来るのかを一緒に考えます。
どんなときも「あなたらしく」暮らしために~やさしい社会福祉入門~
困った時は、「福祉に相談」とは言いますが、ではどこに相談すればいいのでしょうか?
社会福祉はいつでもあなたが「あなたらしく」暮らすことを目指してお手伝いします。
この講義では、「社会福祉」の入門編として解説します。
子育てにおける絵本の効用
近年、高度情報化、核家族化、人々の価値観の多様化などの社会情勢の変化に伴い、子育てに悩みを抱える方が増加していると言われています。
このような中で、親子の絆を深める手立ての一つとして、乳幼児期からの絵本の読み聞かせの効果が注目されています。
この講座は、家庭での絵本の読み聞かせの効用について理解を深める機会となります。
「ぬい撮り」の可能性
スマホなどで、「インスタばえ」する画像を撮影するという行為が一般的になっているが、「ぬい撮り」とは、観光名所、自然風景など様々なものを背景に「ぬいぐるみ」を撮影すること、また、その画像をSNS等で発信することである。この「ぬい撮り」が、地域振興、児童・生徒の郷土学習など、様々な場面で活用できることを実習も織り交ぜて説明する。
中高生向け
中学生、高校生による読み聞かせ活動
・絵本の読み聞かせボランティア活動をするための基本的な知識、技術についての講義、演習
・ボランティア活動を実施するための一般的知識(受け入れ施設との関係づくり、ボランティアの心得など)
自然エネルギー先進地・青森を目指して
自然に恵まれた青森は、風力や太陽光・バイオマスなど自然エネルギーが豊かな地域でもあります。
地球温暖化問題への関心の高まりを背景に、自然エネルギーの導入を支援する仕組みも充実してきました。
この講義では、市民出資による風力発電事業に関わってきた経験から、自然エネルギーの可能性と、地域の資源を産業振興や地域活性化に生かす方法についてお話しします。
NPOでまちを変える―非営利活動入門―
現在、さまざまな公共サービスの担い手として、民間非営利組織(NPO)が注目を浴びています。
NPOはどうやって生まれてきたのでしょうか。いままでの住民運動やボランティアと、どこが違うでしょうか。
県内NPO法人の理事も務めている講師が、いろいろなNPOの実例をもとに紹介します。
“アンケート”にだまされない方法―市民のための社会調査入門―
本来、アンケートやインタビューなどの社会調査を実施するには専門知識や技能が必要ですが、世の中には誤った方法による調査が横行しています。
この講義では、地域社会や組織・集団について調べたり、調査データを利用したりする際のコツを、わかりやすくお話しします。
「人口減少社会の再デザイン」-これからのまちづくり・地域づくり
地方紙記者・社会人院生としての経験を通じて、「人口減少社会の再デザイン」をキーワードに、まちづくり・地域づくりに取り組んできました。
その成果を元に、今後のまちづくりの考え方、地域調査の方法などを解説します。
☆最近の主な研究・活動テーマ:幸畑団地地区まちづくり協議会の活動、空き家調査、JR津軽線沿線の将来像など
新幹線のこれまでとこれから
研究の柱は、東北新幹線(盛岡以北)、北海道新幹線、北陸新幹線などの「整備新幹線」です。
リニア中央新幹線の沿線の一部も調査対象です。
青森県にとっては「通り過ぎた話題」と思われがちですが、北海道新幹線の札幌延伸を控え、青森県や青森市にもさまざまな影響・効果が及ぶと予想されます。
☆最近の主な研究・著作・講演テーマ:北陸新幹線・金沢-敦賀間延伸、青函トンネル、北海道新幹線のこれまでとこれから、医療と新幹線、移住・定住促進と新幹線
災害に負けない地域づくり
NPO法人青森県防災士会の理事を務め、身近なコミュニティと「災害に負けない地域づくり」に関する活動に取り組んでいます。
ゼミにはほぼ毎年、防災士の資格を取得した学生が所属しています。
中高生向け
選挙・投票について考える
青森大学生を対象にした調査や、さまざまな特別授業の実施を通して見えてきた、投票率向上や主権者教育の在り方をめぐるヒントを解説します。
新幹線について
北海道新幹線や東北新幹線、北陸新幹線が地域にどんな影響を及ぼしたのかを、学習活動と関連づけながら解説します。
人口減少社会の再デザイン-若者の地元定着をめぐって
人口減少が地域にもたらす影響と、その対応、特に若い世代への影響や今後の対応について解説します。
特に青森大学生を対象に実施してきた調査に基づき、「地元で働き、暮らす」ことの意味について、ともに考え、論点を探ります。
「色々なジャンルの音楽を聴きながら音楽社会学の世界を知ろう」
日本の47都道府県には1718もの市町村が存在し(令和3年1月1日現在)、それぞれの風土に根差した様々な「まちづくり」を行っています。
その中にあって、数多存在する「都市」という核なる存在は、どのようにして生まれ、そこから何を産み出し、どんな機能を果たしているのでしょうか?
本講義では「都市」いわゆる「まち」について、文化や歴史や人口減少問題などとも踏まえながら一緒に考え、「都市(まち)」の機能等についても論じます。
『地方自治体―繁栄する街・衰退する街―』
人口減少、少子高齢社会に突入しているいま、地方自治体もまた様々な問題を抱え、課題等が山積しています。
しかしながらその一方で、過酷な状況下にあっても市民の福祉向上と住みよい地域社会の構築に向け、種々の「政策・施策」を打ち出しながら繁栄し続けている地方自治体もまた存在します。
本講義では、地方自治体とは何かをやさしく説きながら、現在、様々な事業を展開することで繁栄し続けている街と、その逆に、衰退の一途を辿っている街とを比較しながら、みなさんと一緒に地方自治体を考えていきます。
「色々なジャンルの音楽を聴きながら音楽社会学の世界を知ろう」
実際に様々な世界の音楽を聴きながら、その音楽が生まれた都市・国の風土や文化を探る。
「元気に生きる」ための心理学
「元気に生きる」ことを望まない人はいません。
それなのに、自信を無くしたり、他人を羨んだり、怒ったり、失望したりして、前向きに行動できなくなることもあります。
そんな不健康な状態から脱出して元気になる方法はあるのでしょうか。
本講義では、心理学者アドラーの理論を学びながら、身近な出来事を分析しながら、過去に縛られずに前進できる心の在り方や行動のコツについて一緒に考えていきます。
赤ちゃんが最初に目にするおもちゃを作ろう(ワークショップ)
赤ちゃんは生後1か月までは見えていないと言われますが、発達心理学の研究では、人やモノが30~40cmの距離の場合には認知できることが分かっています。
しかし、この時期の赤ちゃん向けの視覚おもちゃが少ないのが現状です。
色画用紙、紙ストロー、糸、接着剤を利用して、皆さんと一緒に、安全で楽しいおもちゃ作りに取り組みます。
中高生向け
自分らしさって何だろう
青年期は「本当の自分ってなんだろう?」と悩む時期です。
小学生ではあまり経験しなかった孤独に悩み、一方で、何でも語り合える親友を求めます。
こんな矛盾した気持ちに揺れるながら、青年期の心の発達はどんどん進んでいきます。
精神分析学のフロイトやエリクソンの理論をもとに、中高生の日常の事例を引用しながら、「本当の自分」について心理学の視点から迫っていきます。
ご一緒に考えてみましょう。
勇気を持って生きるために
「自分らしく生きたい」と願っていますが、いつも元気になれるわけではありません。
見方を変えてると、生きていることは、未体験の自分と向き合い続けることです。
慣れないことをするのは、悩みや苦しみも伴います。でも、少しの勇気を持てるなら、自分の人生が楽しく充実するのではないでしょうか。
この講義では、見方や立場をちょっと変えることで、勇気をもって生きるヒントを考えることができるはずです。
青森県の近代文学
明治から、大正、昭和、平成、そして令和。今も人気の高い太宰治、寺山修司をはじめ青森県は多くの文学者を輩出し続けています。
青森県ゆかりの作家について、その生涯や代表作だけでなくさまざまな繋がり、ゆかりの地などについて、いろいろな角度から作品を交えて紹介します。
高校生のこころの健康
高校生は、子どもから大人へ移行する時期、心身ともに不安定であるとともに、感受性の豊かな時期です。
この時期の心のきしみ、無気力感、目標の喪失感、無関心な態度、引きこもり、人づきあいが苦手、思春期やせ症などについて共に話し合い、こころの豊かさ、こころの健康について考えてみましょう。
SST(ソーシャル・スキルズ・トレーニング)-よりよいコミュニケーションを身につける-
自分の気持ち、人へのお願いなどをもっと上手に伝えたい、相手の気持ちがわかり、うまく自信をもって人と接したいと思いませんか。人と人との関わり(対人関係)でのストレスを軽くし、
よりよいコミュニケーションの仕方を身につける方法に、SST(ソーシャル・スキルズ・トレーニング)があります。
実際にロールプレイで練習すれば、自分に自信が湧き生活が楽しくなります。よりよいコミュニケーションを身につけてみましょう。
明るい職場・家庭とメンタルヘルス-ストレスとコミュニケーションを考える-
自分の能力を充分発揮し、働きがいをもって楽しく働くこと、明るい家庭で充実した生活を営むことが望まれます。
そのためには、職場の人々、家庭でのメンタルヘルスに関する正しい認識と理解を持ち、的確な対応と、明るい職場づくり、家庭生活が必要です。職場、家庭のメンタルヘルスの問題を解決していくために、メンタルヘルスの基礎知識や対処の方法などの情報を提供し、より明るい職場、家庭を考えてみます。
対人援助のためのケースカンファレンスの方法
対人援助のためにケースカンファレンス(事例検討会・事例研究会)は、必要不可欠です。
福祉サービスの質を、対人援助職としても高めるとともに組織的にも高める上でも、また、多くの関係機関、関係職種によるチームアプローチを実施する上でも効果的です。
ケースカンファレンスを効果的・効率的に実施するための方法のお話しとともに、実際にケースカンフアレンスを開催してみましょう。
中高生向け
思春期のこころの健康
思春期は子どもから大人へ移行する大事な時期です。
感受性の豊かな時期でもあり、心のきしみ、無気力感、人づきあいの難しさなど課題が山積です。
心の豊かさ、こころの健康について考えてみましょう。
よりよいコミュニケーションを身につけましょう。
自分の気持ち、人へのお願いをもっと上手に伝えたい、相手の気持ちがわかり、うまく自信をもって人と接したいと思いませんか。
自分に自信が湧き生活が楽しくなるために、人とのよりよいコミュニケーションを身につけてみましょう。
自分を理解してうまく感情コントロールしましょう。
自分を理解するために、「エゴグラムテスト」「ジョハリの窓」を学習しましょう。
「エゴグラムテスト」で自分のこころの状態がわかります。
「ジョハリの窓」でコミュニケーションの状態がわかります。
自分を理解することで感情をうまくコントロールしてみましょう。
地域イノベーションと持続可能なまちづくり
人口減少や少子高齢化をはじめとする構造的課題や、COVID-19を契機とする社会変革に直面する地域社会。
地方創生、関係人口・移住定住、中間支援団体、DMO、人材育成、ローカルSDGs、コレクティブインパクトなど、
多様な地域イノベーションを創発していくための戦略と持続可能なまちづくりの可能性を考えます。
中高生向け
相手の心を動かすプレゼンテーション
情報を収集し、自分なりの意見をまとめ、他者に伝える力を養います。
相手の心を動かすプレゼンテーションというテーマについて、
①情報を整理する力、②資料に落とし込む力、③自分らしく伝える力の3つの切り口から学びます。
グループワークの併用も可能です。
共感を生むプロジェクトのつくり方
他者と協働し、チームを形成しながら、プロジェクトを企画する力を養います。
共感を生むプロジェクトのつくり方というテーマについて、①心持ち、②考える技術、③コミュニケーションの3つの切り口から学びます。
グループワークの併用も可能です。
地域を元気にする方法
人口減少・少子高齢化の進展する地域社会において、地域の課題を分析し、持続可能なまちづくりを実現していくための視点や事例を学びます。
「認知症」とは?
高齢化率が年々上昇し“超高齢社会”となっている我が国において、「認知症」は決して他人事ではありません。
この講義では、身近な人が認知症になった場合に戸惑わないよう、認知症の症状や対応方法、利用可能な社会資源等をわかりやすく説明します。